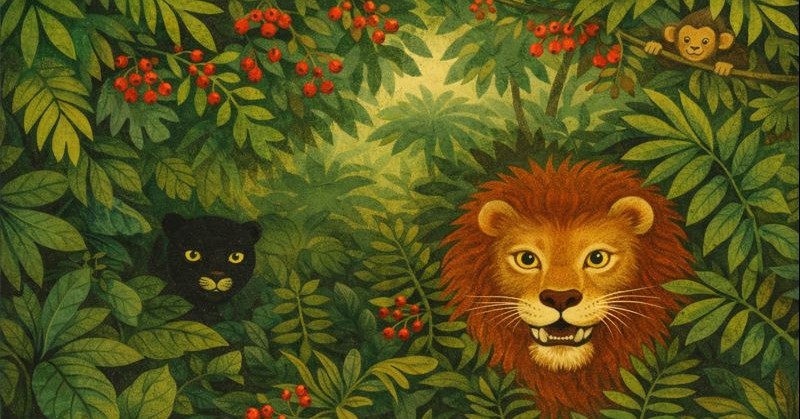Popularitéとvisibilité
8月も終わりですね。暑さの終わりは見えませんが(笑)日射しはやや傾き、秋の光線です(それが暑さとどうもちぐはぐ、ですが...;)
今月も1本論文を書きました。生成AIのテクストをナラトロジーで読むには...というハンドブック風の、読みやすい論文です。いずれ読んでいただく機会もあるといいな、と思っていますが、さて。。;)
Twitterでは書きましたが、この間に、大貫妙子さんについての原稿を打診され、それはもちろん、大貫さんだったら、なにかいいものが書けるなら、ぜひ書いておきたい、という気持ちはあるわけです。
この辺の事情は、80年代末、僕が角川で仕事をしていた当時をご存じの方には、すぐに脈略が判るところでは、と思います。。当時からの読者が、いまここにどのくらい残っているのか、ちょっとよく判りませんが。...実際原稿を打診してきた編集者も、そのあたりとはまったく無関係に、『シティポップ短篇集』からのアイディアだったようです;)
で、生成AIとナレーションの論文を書きながら、一方で大貫さんで何が書けるか、少しずつ考えてもいたのですが、当然ソリッドなレヴュー——ミュジコロジックに、は大変だとしても、ライナーノーツよりもうちょっと論文寄りの原稿も、まぁ、書けるわけです;)
でも、僕が大貫さんの話を書くのなら、やっぱり個人的な記憶の話もあったほうがいいんじゃないか。原稿としてより面白くなるだけでなく、80年代を知らない人には、そのほうがもはや興味深いのではないか(「歴史的」過去の時代の証言としてw)という気もしてきました。
そうすると、では、まず、最初に大貫さんと会った時の話。これはあったほうがいいのかもしれない。。と考えて、そこで「...え。でも、その話、ほんとに書くの?」と立ち止まりました。
つまり、大貫さんに最初に会ったときの思い出、というのは、僕にとっては、とにかく、大貫さんに叱られたという思い出だからです(笑)