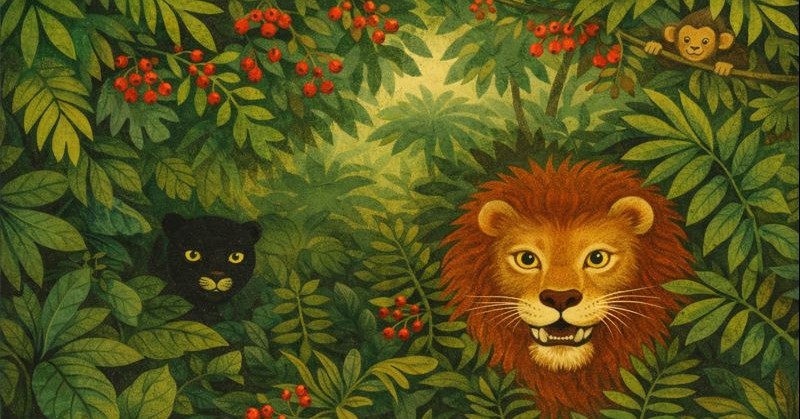80年目の夏に。〜世界を照らせ、理性の光
10年前の8月、「70年目の夏に。〜日当たりのいい女の子の学校」という原稿を自分のホームページにポストしました。
これは僕のHPにFacebookのライクを設置して以来、これまでで一番多くのライクを付けていただいた、記念すべきポストです(https化により、残念ながら、そのライクは表示されなくなってしまいましたが。...100ライク程度です・笑)。
このポストを書いたのは、実は、パリで戦後70年、ノルマンディー上陸作戦70年周年記念の式典をTVで見て、非常に考えさせられるものがあったからです。
あれから10年。今年はこの上新しく、不戦、非戦、反戦のことばを語ることは難しい。とりわけポスト・トランプ時代の今日にあっては...。そう、思うともなく、思っていました。
しかし、いいアイディアがあった時にだけ書けばいい、というベースラインを基本的に守って生きてきている僕とは違い、いいアイディアがない、では済まない人たちがいます。
政治家とは、本来、そういう人たちでしょう。
今年(2025年)の広島平和記念式典での広島県知事のスピーチを聞いて、これもまた、非常に考えさせられるものがありました。
ニュースなどで聞かれた方、感銘を受けたという方もいるのではないか、と思いますが、このスピーチは、感情を背後に抱えつつ、全体を理性で語り切るという、そして、語り切るだけの構成力、たしかな構造を持つ、普遍的な言語で語られた、かくあるべし、という平和へのメッセージとなっていました。
いや、正直いって、こんなスピーチのできる政治家が日本にいるとは、まったく思ってもいませんでした。不明を恥じる次第です。
これは、日本の政治史に残る、記念碑的なスピーチ(ディスクール)だろうと思います。
なぜそこまでいうのか。
このスピーチのどこがそんなに??と思う人はもちろん、「そうだな、たしかにあれはいいスピーチだったな...」と思う人も、改めて、僕のアナリーズを読んでみてください。
ひとつひとつ、パートに分けて丁寧に分析していきます;)
まず、全体の動画を貼っておきますが、このスピーチが素晴らしかったのは、この現代の厳しい状況をしっかりと踏まえながら、一昨年(2023)年広島サミットでの、同じ広島県出身とされる当時の日本国首相の〝核抑止力肯定〟宣言を、理論的に可能なかぎり押し戻したこと。
そしてその全体を、情緒ではなく、ロジックという、人類の普遍的な言語で、理路整然と詰めていった、ということ。ここが非常に新しかったわけです。
以下、順にそれぞれ見ていきます。(スピーチ全文も最後に貼っておきます)
まず、スピーチは、現在の厳しい状況を直視することから始まります。
法と外交を基軸とする国際秩序は様変わりし、剥き出しの暴力が支配する世界へと変わりつつあり、私達は今、この繁栄が如何に脆弱なものであるかを痛感しています。
これはもちろん、ロシアのウクライナ侵攻や、イスラエルのガザ攻撃、そしてアメリカのイラン爆撃など、現代が戦争の時代に入っていることを指しています。
トランプは、強いものがルールを決めるのは当たり前だろう、とさえいいました。
それは獣の世界の〝当たり前〟です。人は誰しも独善的なものですが、それでも弱い人が虐げられているのを見ると胸が痛む。理不尽かもしれません。偽善的かもしれません。でも、それが人間の自然な心であり、人間らしさです。これがなければ、人間は獣と何ら、変わりません。
トランプがいっているのは、要するに、向こうから来た強い人が僕を殴ってもいい。あなたの財布を盗ってもいい。強いものが弱いものより強いのは当たり前だろう...と、こういうことです。
これは非人間的な感覚であり、マフィアや暴力団、犯罪者の〝常識〟です。
人は誰しも弱い子どもとして生まれ、弱い老人として死んでいく。弱さは、人の本質です。その人間なら誰にでも判る事実を想像することのできない、獣の発想です。
このような世の中だからこそ、核抑止が益々重要だと声高に叫ぶ人達がいます。
そうなのです。これも現在の厳しさです。日本の上には、北朝鮮のミサイルがびゅんびゅん飛んでいる、という話です。いまは飛んでないかもしれませんが、そういうことをいわれて、非武装だ、専守防衛だ、などというと、頭の中がお花畑、という例の常套句が待っています(...しかしそう嘲る人の頭の中のほうが、実はよっぽど〝ファンタジー・ランド〟、つまり、その〝現実〟は架空のフィクションであり〜ということが、すぐあとに論じられるわけですが;)
また、日本の人口減は政策的な失敗で、もはや歯止めがかけられません。そして世界の人口は増えています。人がいない〝空き地〟があれば、そこに誰かが入ってくるのは自然です。
アメリカはもちろん、フランスと比べても、日本には外国人はほとんどいない、といっていいようなものです。パリのメトロの車両の中では、フランス人の顔を探すほうが難しいことはふつうにあります。それでも日本人の感覚では、外国人がどんどん日本中に増えている、という脅威を感じるのは判ります(でも、それは、欧米に住んだことがないからなのですが!)
スピーチは、しかし、この状況を踏まえて、
しかし本当にそうなのでしょうか。
と切り返します。そして、
確かに、戦争をできるだけ防ぐために抑止の概念は必要かもしれません。
と一旦理性的に譲歩(concession)した上で、
一方で、歴史が証明するように、ペロポネソス戦争以来古代ギリシャの昔から、力の均衡による抑止は繰り返し破られてきました。
と、歴史・事実を持ち出します。そして、ここがひとつのピーク・ポイントとなるのですが、
なぜなら、抑止とは、あくまで頭の中で構成された概念又は心理、つまりフィクションであり、万有引力の法則のような普遍の物理的真理ではないからです。
この否定のしようのない正論をぶつけてきます。
これは、非常に厳しいところです。政治家とはいえ、広島県知事という、地方の政治家だからこそいえたことであり、また一昨年の愕然たる、岸田核抑止力肯定宣言があったから、あれをバランスするため、打ち消すためにこそ、この正論をぶつけざるをえなかったのではなかったか、と思います。
つまり、抑止力は、確かにフィクションであり、ゲームのルール、いわば〝ごっこ〟遊びで、みんながそれを信じているフリをしなければ、その瞬間に消えてしまうわけです。
(そんなことをいったって、現にこれまで核兵器は使用されなかった。だから抑止力はフィクションじゃなく、現実に存在してるじゃないか、という人もいるかもしれません。うん、だから、今ちょうど、そのことをいってるわけです。つまりそれが「みんながその〝ゲームのルール〟を守ってこれまで〝プレイ〟してきた」ということです。誰もが明日、「一抜けた!」といって止めることのできる〝ごっこ〟遊びなわけです・笑)
その一方、核抑止力を肯定してしまうと、今度はその瞬間に、核兵器廃絶への道は絶たれてしまいます。つまり、核兵器の存在こそが核戦争を抑止している、というかたちで、核兵器保有を必然化してしまうわけですから。核兵器の廃絶は、永遠に手の届かない、ただの〈夢〉になってしまいます。だからこそ、これまで世界の政治家は、核抑止力を否定もしない代わりに肯定もしない、という曖昧な態度をとってきた。つまり、それがある種の〝知恵〟だったわけです。
その誰もやらなかった、あるいはできなかったことが2023年にできた、やってしまった、というのは、それが世界最初の核攻撃による被爆地、広島で開かれたサミットで、そして日本の首相がその犠牲の地・広島の出身者ということだったからこそ、ではないでしょうか。
そう考えると、これは、ほとんど犯罪的、それも人類史における致命的な重罪のようにさえ思えてきます。
そしてその「犯罪行為」があったからこそ、今回の広島県知事のスピーチは、政治家としていってはいけないその正論をおそらくぶつけてきたわけです。つまり、抑止力はフィクションでしかない、という真実を、です。
これでよかったのだと思います。針が反対側に振り切れてしまったのだから、ここではどんな手を使ってでも、少なくとも0の位置まで押し戻してやる必要があったわけです。このスピーチは、それに成功した、と思います。
そして、
自信過剰な指導者の出現、突出したエゴ、高揚した民衆の圧力。あるいは誤解や錯誤により抑止は破られてきました。
まず、このように欧米や日本でのポピュリズム台頭の現状にしっかりと一瞥を加えた上で、ここからは再び事実に照らして、抑止力は幻想である、との自説を担保していくわけですが、その頭に置かれた、
我が国も、力の均衡では圧倒的に不利と知りながらも、自ら太平洋戦争の端緒を切ったように、人間は必ずしも抑止論、特に核抑止論が前提とする合理的判断が常に働くとは限らないことを、身を以て示しています。
...まさにこれは、僕の世代にとっては〝常識〟というべき事実です。
世界のどの国が抑止論を信じたとしても、真珠湾攻撃を決行した日本人の末裔が、真面目な顔で抑止力、などと口にするのは笑止千万という以外ありません(笑)
そして、それに続く、
国破れて山河あり。... 国守りて山河なし。
この対比も、実に鮮烈です。いや、よくいった、というか、この鮮やかな警句は、この問題を本当にちゃんと考えていなければ出てこない、見事な箴言ではないか、と思うのです。
そしてまた、ここには第二次世界大戦以来の日本の問題が的確に要約されているのではないでしょうか。
日本は組織が何のために存在しているか、ではなく、いかにしてその組織を守るか、という本末転倒を延々と続けている。
例えばひとつの省庁が、日本人がいなくなっても、さらには日本という国がなくなっても、まるで存在し続けるかのように、その組織自体の存続を目的化し、その目的に対して合理化が行われている...。そう疑われる節さえあります。
次の、
かつては抑止が破られ国が荒廃しても、再建の礎は残っていました。国守りて山河なし。もし核による抑止が、歴史が証明するようにいつか破られて核戦争になれば、人類も地球も再生不能な惨禍に見舞われます。
ここはやや苦しい、ぎりぎりの妥協点、なのでしょう。よしんば抑止力全体を否定しないまでも、せめて核兵器だけは別枠にせんという、広島県知事としては、最低限、ここだけは達成しなければならないタスクだったのだろうと思います。
概念としての国家は守るが、国土も国民も復興不能な結末が有りうる安全保障に、どんな意味あるのでしょう。抑止力とは、武力の均衡のみを指すものではなく、ソフトパワーや外交を含む広い概念であるはずです。そして、仮に破れても人類が存続可能になるよう、抑止力から核という要素を取り除かなければなりません。核抑止の維持に年間14兆円超が投入されていると言われていますが、その十分の一でも、核のない新たな安全保障のあり方を構築するために頭脳と資源を集中することこそが、今我々が力を入れるべきことです。
ここも、正論のオンパレード、目白押し、です(ひたすら正しいことだけを述べています・笑)。
そしてここまでが、このスピーチのいわば「理論」パートです。結論の跳躍を支える、土台になります。
次いで、いよいよ、コンクルージョンの展開部。ここで大きく切り返して、クライマックスを作るわけですが、、
みなさんはここをどうお感じになったでしょうか。
核兵器廃絶は決して遠くに見上げる北極星ではありません。
はい。ここに「北極星」という比喩が出てきます。
欧米の文学や哲学を学んだ人なら、これがメトニミー、換喩である、ということがぱっと理解されると思います。ここでガツン、とこのスピーチ、ディスクールがツボに入るわけです(笑)
つまり、「理論」の上に「修辞」が乗ってくる。まさにスピーチ展開部のお手本的な展開です。
「北極星」は、道標です。いつもわたしたちを導きますが、そこにたどり着くこと自体は目的ではない。ただその方向を、いつも変わらず、正しく知らせてくれれば、それでいい。
つまり、この比喩の含意は、核廃絶を、そういう純粋な、到達不能な目標にしてはならない、ということです。
被爆で崩壊した瓦礫に挟まれ身動きの取れなくなった被爆者が、暗闇の中、一筋の光に向かって一歩ずつ這い進み、最後は抜け出して生を掴んだように、実現しなければ死も意味し得る、現実的・具体的目標です。“諦めるな。押し続けろ。進み続けろ。光が見えるだろう。そこに向かって這っていけ。”
そして、今度は対比、コントラストです。「北極星」という天の光に対して、瓦礫の上の光は、地上の光、いわば、手の届く、辿り着くことのできる光です。
最後にノーベル平和賞受賞の被団協、サーロー節子の引用に抜けていくあたりは、もう、圧巻です。
換喩、コントラスト、引用。
これはまさに、フランスの国語教育の初等教育が教えることであり、このスピーチを聞いて、国語、文学のできるフランス人が、ほとんど無意識に気づくことでしょう。
フランスの国語では、作者や語り手が「何をいいたかったか」を考えさせようとはしません。
作者や語り手の「いいたかった」ことは、文学的なテクストには書いてありません。つまり、そこには明示的な「正解」はないわけです。
そうではなくてこのように、比喩や対比や引用といった誰にでも判る、明示的な、見落としてはならない要素を見つけ出し、それを分析していくトレーニングから始めます。そういう、明示的な「正解」のある要素を読み分けていく。
つまり、「何がいいたかったか」ではなく、テクストが「(現に)何をいっているか」、あるいは、「何をいって(しまって)いるか」を読む力を育てるのが、フランスの国語の授業です。
「何をいっているか」を正確に読んでいくうちに、いいたいことや、いうべきことは、どのようにいわれるのか、どのようにいえばよいのかということが、少しずつ身についていきます。自分でも、じゃあ、どう書けばいいかが判ってくる。これがフランスの国語教育の考える、文章力です。
伝える力は、読み手の受容を想像する力ではなくて、まず、自分のいいたいことを十全にいいきる力です。自分のいいたいことを十全にいいきる能力のない人が、相手の受容をあれこれ慮ったところで、一体何ができるというのでしょう? 慮って「そうか、こう書けば受容されるんだ!」と判っても、今度は、その判った通りに十全に書き表す力が必要になるはずです;)
換喩、コントラスト、引用、と見事に固められた、このお手本のようなスピーチの結びは、あるいはあまりに知的に構成され、理屈っぽいと思う人もいたかも知れません。
しかしこれは、フランス人にも、アメリカ人にも普遍的に理解されるひとつの言語、ロジックという言語でもあります。
たとえば、同日に行われた、広島市長の平和宣言も、日本的に考えれば、決して悪い演説ではなかったと思います。情緒に訴え、共感を求める。心のこもったスピーチだったといってもいい。
でも、こういうことは、戦後ここまで、ずーーーーっとやってきたわけです。その結果、ナショナリズムを謳う政党が大衆の支持を集めているわけです(ナショナリズムは英語やフランス語ではファシズムのいい換えなので、欧米人に使うときは気をつけて!)。
情緒や共感も、あるいはある程度、人類共通の、普遍的な「言語」——ランガージュ、といってもいいかもしれません。しかし、情緒や共感は、オープン・エンドなのではないでしょうか。つまり、感情や思いには、強さはあっても、「正解」はない。
たとえば、戦争反対に、「とにかく死ぬのやだもんね」というコピーを付けたのはたしか70年安保世代の人だったように思います。しかし「死ぬのは嫌だ、戦争反対!」というこの「情緒」は、強力ですが、その同じ感情が、そのまま「戦争するしかない!」となることもあるのは当然なのではないでしょうか。
戦争の悲劇に胸を痛めれば痛めるほど、絶対に愛する人をこんな目に遭わせてはならない、という情動から、軍拡こそが大切だ、軍備で守るしかない!という「答え」は常に容易に出てくるように思います。
では、それが「間違っている」といえるのは何なのか。
つまりそこに「正解」を見出すことができるのが(少なくとも、できると仮定できるのが)、ロジックであり、理性です。
このあとは──
・なぜ日本人は「ことば」を信じないのか?
・湯崎スピーチが見せた、修辞技法の力
...そして最後に、本稿を締めくくるコンセプトとして、
・「ロジックとは詩である」という、美しい飛躍へと至ります;)