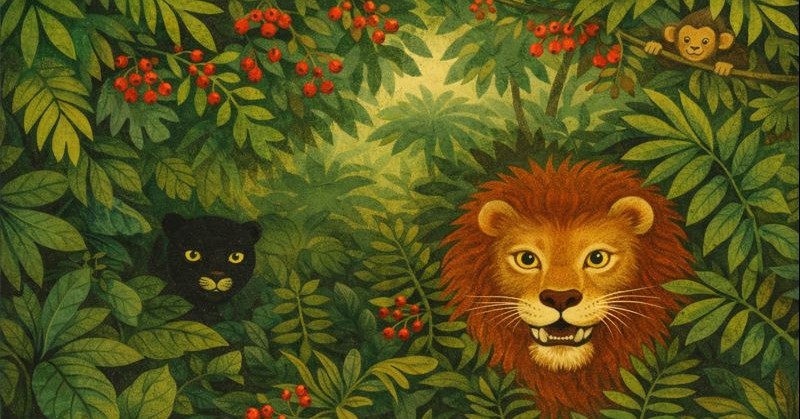6月の終わりに。〈聞こえない声〉と生成AIの見えづらい関係
こんにちは。雨降りの季節ですね。
先月の先行研究確認に続いて、今月はどーんと時間をとって、今年の論文、本文を書いてきました。予想よりもかなり長い、原稿用紙70枚程度の大・小論文になってしまいましたが(笑)、ほとんど一気に書いてしまいました。しかしふと気づけば6月ももう終わり。このタイミングで、ニュースレターを送っておきます。近況報告というか、「今月書いたこと」。近況は、書いたことしかありませんので(笑)
今回の小論文、どうかなぁ...と思いながら書いていましたが、博士論文を含め、これまでに理論的には相当〝外堀〟は埋まってきましたので(笑)そろそろ「その結果、どういう事態が訪れるか」というあたりを具体的に書いてもいいんじゃないか、
いきなり「そこ」を書いたら誰も本気にしない、重要性、意味が判らないとしても、ここまで細かく理論を積み重ねてきたので、そろそろ〝その結果〟の話をしても、一概にバカバカしい、ただの空疎な思いつきだろう、とはとらない人も出てくるのではないか、、と思って書いてみましたが。。
いや、これはどうだろう。たとえば東大の総合文化の言語情報は、日本の高度な文学研究機関の中でもいちばん先進的、というか〈非人称の語り〉つまり、人格的な語り手を持たない小説の叙述(ナレーション)みたいな考え方に許容力のある先生方が集まっているように思うのですが。。
しかし、こうなると、どうだろう、、というのも、今回は一人称小説のノン・コミュニケーション性、〈非人称の語り〉。。つまり、「語り手不在」を論じてしまっているからです。
語り手がいない「一人称」の語りなど、従来の物語叙述の見方からいえば、ほとんど自己矛盾、定義的にありえない、ということになりそうではないでしょうか?(笑)