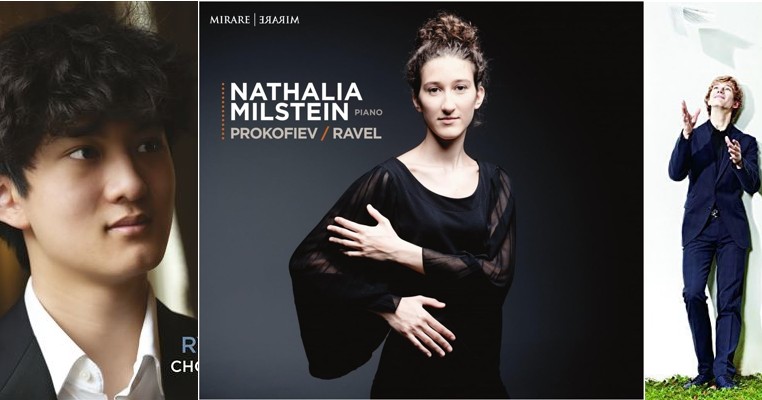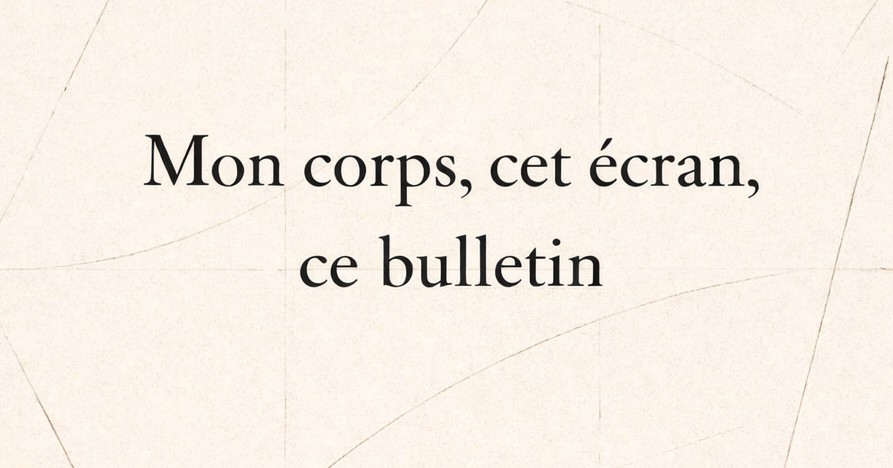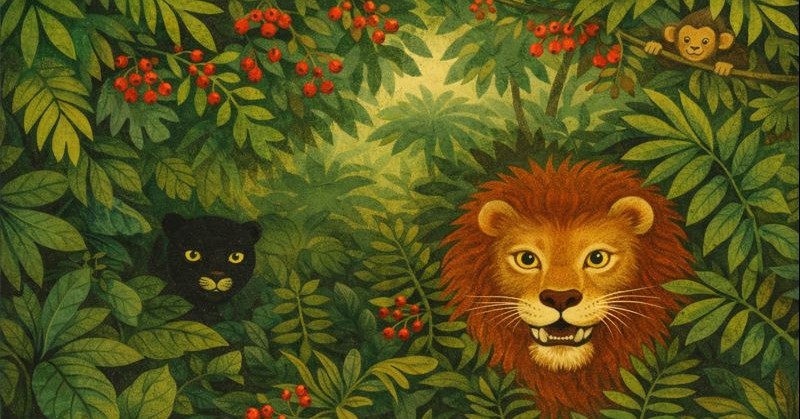「本音」なんてものがあると考える自体、もはや前世紀的(でなかったら、言語センスが大体過ぎ)。
これもだいぶ前に書きかけて、放置していたニュースレター。内容的に、過去の視点にもとづく部分もありますが、書きあげたので配信します。...というか、書きあげた部分のみ配信、というべきか?w(なお、論文ではなく、#雑談 です!)
昨年、米大統領選の結果を受けて、FBページに「本音の時代」の始まりか?とポストした。
日本人は一般に「本音」をより重要で本質的なものとして重視しているが、実際には、この新(再)米大統領(政権)の剥き出しの「本音」には、日本人の繊細な感性は耐えられないのではないか、とあの時は書いた。
要するに、現在の米大統領(45・47代)には、自分の損得以外に何のロジックもない。何がどうなっても、自分の中でそれが得である、と収支が合えば、それでいい。
その露骨なマインドセットによる権力行使を、やや婉曲的に「本音」そのままの政治、と呼んでもいいように思ったのだが、ただし、その「本音」というのは「得をしたい!」という点では一貫していても、具体的には、その場その場で場当たり的に変わっていく考えだ。考え、というより、むしろ「思いつき」のようなものだといってもいい。
面白いなと思ったのは、CNNなんかを見ていても、ゲストとして出てくる事情通が、当然主にはアメリカ人だが、この新(再)大統領について意見を求められコメントする際、まず「大統領の頭の中に入ることはできませんが」と非常にしばしば前置きすること。このあたりも、アメリカ人と日本人の、世界の西端と東端で、不思議に共通する親和性のひとつ、という気がする。
ヨーロッパ人、少なくともフランス人は、こういうことはいわないように思うのだが、その理由は、そんなことわざわざ断るまでもない、自明のことだから。「人の頭の中に入れる人」などどこにもいない(笑)
これは僕も時々いってしまうが、「個人的には」という前置きと同じで、個人を越えた普遍的な見解などそう容易くいえるわけもないのだから、「個人的には...」とわざわざいうほうがかえって謙虚ではない、傲慢になる。それと同じ理屈だ。
とはいえ、この「人の頭の中に入る」問題(??)は、そのまま、黒田成幸 aka S.-Y. Kuroda のいう〈報告〉〈非報告〉のコンセプトとも重なってくる:
日常の会話(コミュニケーション)では「私は寂しい」と自分の気持ちを一人称で報告することはできても、「マリは寂しい」と、三人称で人の心の状態を報告することはできない。これが日本語の〈人称制限〉と呼ばれる現象で、
しかしそれが物語、小説文では、「マリは寂しかった」と、「私」以外の内面を三人称で確定的に述べること、表象することができる、というのが黒田が日本語に見出した、日常の会話とは異なる「文法」を持つ、非コミュニケーション的な「物語の言語」だった。
〈人称制限〉のある日本語を母語とする日本人には、比較的納得しやすい話だろう。
...つまり、「私は寂しい」というのは「私」が私の心の状態を伝えている、〈報告〉=コミュニケーションであるのに対し、「マリは寂しかった」というのは、マリが寂しかったという物語内の・物語の上でのひとつの「事実」を〈非報告〉に表している。
何か「事実」がまずあって、それを報告している、伝えている、ということではなく、むしろ「マリは寂しかった」と物語文、小説文にそう書かれているということ、それ自体が「マリは寂しかった」という、その物語における「事実」となる。マリが物語の中の架空の人物でしかない場合、とりわけそうだろう...。
これが、〈非報告〉的な文はコミュニケーションではない(=ノン・コミュニケーション)という意味で、つまり、それが〈ナラティヴ〉といういうことだ。
しかし「人の頭の中」、たとえば、大統領の「頭の中」に入れる人がいるかいないか、というより以前に、そもそも自分自身だって、はたしてそう簡単に「自分の頭の中」に入れるか、という問題がここにはある。
G・ライルの『心の概念』は、心身二元論を批判する「機械の中の幽霊」ということばであまりにも有名だが、